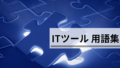本記事では、オンラインホワイトボードツールとして注目される「Miro」について、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説しています。
Miroとは?
Miroとは、チームでの共同作業を視覚的かつ直感的に行うことができるオンラインホワイトボードツールです。付箋や図形、テンプレートなどを活用して、アイデア出しやプロジェクト管理をスムーズに行えます。
わかりやすい具体的な例
新商品のアイデアをチームで出し合うとき
graph TD A[チームミーティングを開始] --> B[Miro上にホワイトボードを作成] B --> C[付箋機能で各自がアイデアを出す] C --> D[図形や矢印で関係性を可視化] D --> E[優先順位を話し合いながら整理] E --> F[プロジェクトに落とし込む] note right of A ※ホワイトボード:画面上の自由に編集できるスペース ※付箋機能:アイデアを短文で記述できるツール
例えば、新商品のアイデアを出すときに、Miroを使えば全員が同時に付箋で意見を書き込み、矢印でつなげることでアイデアの関係性を見える化できます。リアルタイムで編集できるので、議論が活性化されます。
遠隔地のプロジェクトメンバーと一緒に計画を立てるとき
graph TD A[オンライン会議の開始] --> B[Miroボードを共有] B --> C[タイムラインテンプレートを挿入] C --> D[担当者がタスクを追加] D --> E[進行状況を視覚的に確認] note right of C ※テンプレート:あらかじめ用意された図表の型 ※タイムライン:時間軸に沿ってタスクを整理する手法
プロジェクトチームが地理的に離れていても、Miroを使えば同じタイムライン上にタスクを並べて可視化できます。メンバー全員が理解しやすく、進捗管理もしやすくなります。
Miroはどのように考案されたのか
Miroは、リモートワークの拡大とチームコラボレーションの変革に対応するために生まれました。従来のホワイトボードや付箋紙では不十分だった遠隔チーム間のアイデア共有やビジュアル思考を、オンライン環境で再現・拡張する目的で設計されました。
graph LR A[リモートワークの急増] --> B[既存のコラボレーションツールの限界] B --> C[視覚的思考の重要性が注目] C --> D[Miroの開発がスタート] D --> E[グローバル展開] note right of B ※視覚的思考:図やアイコンを用いて思考を整理する方法
考案した人の紹介
「Miro」は、ロシア出身のAndrey Khusid氏によって考案されました。彼は自身のデザインスタジオの中で、クライアントとアイデアを共有する手段に課題を感じ、より直感的にコラボレーションできるオンラインツールの必要性を痛感したことからMiroの開発に至りました。2011年に設立されたRealtimeBoardを前身として、後にMiroに改名され、世界中の企業に広まりました。
考案された背景
2010年代前半、世界的にデザイン思考やアジャイル開発が注目され、ビジュアルな共同作業へのニーズが高まりました。また、スタートアップ企業の急成長により、地理的に離れたチームでのリアルタイムな情報共有の重要性が増し、オンラインホワイトボードのようなツールの必要性が高まっていました。
Miroを学ぶ上でつまづくポイント
多くの人が最初につまずくのは、操作できる要素が多く、何から使えばよいかわからないという点です。付箋、図形、テンプレート、コメントなど豊富な機能があるため、慣れるまでに時間がかかることがあります。また、FigmaやNotionなど他のツールとの連携機能も豊富ですが、初学者には複雑に感じられるかもしれません。まずは付箋を使ったアイデア出しから始め、徐々に機能を広げていくのがコツです。
Miroの構造
Miroは、クラウドベースのアプリケーションで、リアルタイムコラボレーションを可能にするWebSocket通信や、テンプレートベースのUIライブラリで構築されています。ユーザーごとに権限が設定できるボード構造と、各種ウィジェット(付箋、図形、画像など)を自由に配置・操作できるアーキテクチャが特徴です。
graph TD A[ユーザー] --> B[ボード] B --> C[付箋ウィジェット] B --> D[図形ウィジェット] B --> E[画像ウィジェット] A --> F[WebSocket通信] note right of F ※WebSocket:双方向通信を可能にする技術 ※ボード:ユーザーごとに共有・編集できるキャンバス
Miroを利用する場面
主にアイデア出し、プロジェクト設計、遠隔会議の可視化などに活用されます。
利用するケース1
デザインワークショップをオンラインで開催する際、Miroを使って複数の参加者が自由に意見を書き込んだり、テンプレートを活用して課題整理を行うことで、全員が能動的に参加できる場を作れます。事前にテンプレートを用意しておけば、参加者はガイドに従ってスムーズにアイデア出しができます。リアルタイムでの共有により、意思決定のスピードも上がります。
graph TD A[ワークショップ開始] --> B[テンプレートを準備] B --> C[参加者が記入] C --> D[ファシリテーターが進行] D --> E[意見を分類・整理]
利用するケース2
プロジェクトの初期設計フェーズで、ステークホルダーと要件定義を共有するためにMiroを活用する企業も増えています。Miro上でワイヤーフレームやマインドマップを作成しながら、関係者とリアルタイムで意見を交換することで、認識のずれを防ぐことができます。文書でのやり取りよりも直感的に共有できる点が高く評価されています。
graph TD A[要件定義ミーティング] --> B[Miroでワイヤーフレーム作成] B --> C[ステークホルダーがコメント] C --> D[フィードバックを反映] D --> E[設計方針の確定]
さらに賢くなる豆知識
Miroには教育機関向けの無料プランが用意されており、大学や高校でも活用が進んでいます。また、Miroverseと呼ばれるユーザーが作成したテンプレート集が存在し、公開されているボードをコピーして使える機能があります。これにより、初心者でもプロが作成したフレームワークを活用し、質の高い作業が可能になります。
あわせてこれも押さえよう!
Miroを深く理解するためには、関連するツールについても学ぶことが重要です。ここでは、併せて学ぶべき5つのツールを紹介します。
- Figma
- Notion
- Slack
- Trello
- Zoom
デザイン作業に特化した共同編集ツールで、Miroと連携して画面設計やUIレビューが可能です。
情報整理やタスク管理に使われるノートツールで、Miroと併用することでプロジェクトの全体像を見える化できます。
チームコミュニケーションに使われるツールで、Miroとの統合で通知やボードの共有が簡単になります。
タスク管理に特化したボード形式のアプリで、Miroとの併用で進捗の可視化が強化されます。
ビデオ会議ツールで、Miroを画面共有して会議中にホワイトボードを使ったディスカッションが可能です。
まとめ
Miroを活用することで、チームの創造力や生産性を飛躍的に高めることができます。視覚的にアイデアを整理しながら、メンバーとリアルタイムに意見交換ができるため、合意形成のスピードも向上します。今後の働き方を考える上で、Miroの理解は非常に価値あるものとなります。