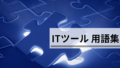本記事では、コンテンツ制作を効率化するツール「GatherContent」について、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説いたします。
GatherContentとは?
GatherContentは、複数の関係者と共同でWebコンテンツの作成・編集・管理を行うためのクラウドベースのツールです。ワークフローの一元管理が可能で、CMSへのコンテンツ移行作業を効率化します。
わかりやすい具体的な例
わかりやすい具体的な例1
企業のWeb担当者が、外部ライターやデザイナーと協力して新しいキャンペーンページを作る際、GatherContentを使えば、誰が何をいつまでに担当するかが一目でわかります。Googleドキュメントやメールでのやり取りが不要になり、作業の抜け漏れが減ります。プロジェクト管理とコンテンツ制作が同時に進行できるのが魅力です。
graph TD A[Web担当者] --> B[GatherContent] B --> C[外部ライター] B --> D[デザイナー] C --> E[記事制作] D --> F[画像制作] B --> G[納期管理] G --> H[CMS連携] note right of B: すべてのコンテンツ制作工程を一元管理
GatherContentでは、関係者が一つのプラットフォームで同時に作業できるため、メールでのやり取りやファイルのやりとりが不要になります。納期管理やコンテンツの進捗がリアルタイムで確認できる点も初心者にとって安心です。
わかりやすい具体的な例2
大学のWebサイトを更新するプロジェクトで、各学部からの原稿提出が必要なケースを考えてみましょう。GatherContentを使うことで、各学部に専用の編集画面を割り当て、提出期限やテンプレートに沿って記入を促すことができます。校正作業も一元化され、Webチームの作業負担が大きく軽減されます。
graph TD A[学部担当者] --> B[テンプレート入力] B --> C[レビュー待ち] C --> D[校正者レビュー] D --> E[承認] E --> F[公開準備] note right of A: 部門別に分けた入力・確認が可能
このように、学内のさまざまな担当者が異なる場所にいても、GatherContent上で原稿を記入・確認・承認まで行えるため、紙やメールを介した面倒なやり取りが不要になります。
GatherContentはどのように考案されたのか
GatherContentは、Web制作プロジェクトの混乱や非効率を解決するために考案されました。特に大規模サイトにおけるコンテンツの進捗可視化と品質維持が課題とされ、効率化の必要性から誕生しました。
graph TD A[従来のWeb制作] --> B[非効率なコミュニケーション] B --> C[納期遅延] C --> D[クライアント不満] A --> E[GatherContentの必要性] E --> F[一元管理の発想] F --> G[ツール開発へ] note right of G: クライアント管理と制作進行を一本化
考案した人の紹介
GatherContentを考案したのは、スコットランド出身のWeb制作専門家キース・ペイブリー氏です。彼はクライアントとの間で繰り返される納期遅れや指示の食い違いに課題を感じ、2009年に自らのエージェンシー経験を活かしてGatherContentを開発しました。現在では世界中の制作現場で活用されています。
考案された背景
2000年代後半、Web制作業界ではCMSの普及とともに、コンテンツ制作の分業化が進みました。特に企業のWebリニューアルでは、関係者が多くなることで進行の混乱が起きやすく、情報の一元管理の必要性が高まっていました。GatherContentはこの問題に対応するために登場しました。
GatherContentを学ぶ上でつまづくポイント
多くの初心者が最初につまづくのは、「コンテンツモデル」や「ステータス管理」といった機能の意味がわからない点です。たとえば「コンテンツモデル」とは、記事のタイトル・本文・画像などを構造化して管理する仕組みのことですが、CMSに慣れていない人には馴染みがありません。また、「承認」や「レビュー」などのステータスを適切に使い分けることも慣れが必要です。
GatherContentの構造
GatherContentは「プロジェクト」「コンテンツ」「フィールド」「ステータス」という4つの主要要素で構成されています。プロジェクト内でコンテンツを作成し、各コンテンツはフィールド(例:見出し、本文、画像など)で構成され、ステータスによって進捗を管理します。
graph TD A[プロジェクト] --> B[コンテンツ1] A --> C[コンテンツ2] B --> D[フィールド:タイトル] B --> E[フィールド:本文] B --> F[ステータス:レビュー中] C --> G[フィールド:画像] note right of A: 全体構成を視覚化して制作フローを明確に
GatherContentを利用する場面
GatherContentは、複数人でのコンテンツ制作やWebサイトリニューアルなどの場面で活用されます。
利用するケース1
企業のマーケティングチームが、キャンペーン用の特設サイトを立ち上げるとき、GatherContentを使えばチームメンバーが共同で記事や画像を作成し、承認フローまで一元的に管理できます。特にSEO対策やブランドトーンの統一が求められるケースで有効です。
graph TD A[マーケチーム] --> B[記事作成] A --> C[画像制作] B --> D[レビュー] D --> E[承認] E --> F[公開用データエクスポート] note right of E: CMSや他の配信システムへ連携可能
利用するケース2
自治体のWebリニューアルにおいて、住民向けの情報ページを複数部門で更新する必要がある場合、GatherContentを導入することで部門ごとの原稿提出・校正・承認がスムーズに進行します。役所特有の確認フローも柔軟に対応できる点が評価されています。
graph TD A[各部門] --> B[原稿入力] B --> C[校正担当] C --> D[責任者承認] D --> E[CMS公開] note right of D: 行政文書に特有の承認フローも管理可能
さらに賢くなる豆知識
GatherContentはZapierなどと連携することで、Google SheetsやSlackとの自動化も可能です。たとえば、特定のステータスになったコンテンツを自動でSlackに通知したり、Google Sheetsで一覧表示して進捗確認をするなど、外部サービスとの連携でさらに効率的に運用できます。
あわせてこれも押さえよう!
GatherContentを効果的に活用するには、あわせて学ぶべき関連ツールを理解しておくことが重要です。
- WordPress
- Contentful
- Trello
- Zapier
- Google Sheets
代表的なCMSで、GatherContentからのデータ移行対象として頻繁に使われます。
APIベースのCMSで、構造化コンテンツとの親和性が高く、連携もスムーズです。
コンテンツ制作のタスク管理に使われ、進捗を可視化するツールとして補完的に活用されます。
GatherContentと他ツールをつなげる自動化ツールで、通知や一覧生成に便利です。
コンテンツ進捗や担当一覧などを表形式で管理し、レポート作成に役立ちます。
まとめ
GatherContentを理解することで、複雑なコンテンツ制作の現場を効率化できます。チーム全体の作業が可視化されることで、ミスや遅延を防ぎ、より品質の高いWebコンテンツを提供できるようになります。プロジェクト成功に欠かせないツールとして、ぜひ活用を検討してみてください。