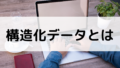みなさんこんにちは。
副業ブログのaksyaです。
本日は
『【概念編】SEOとは?|副業ブログ』
について解説していきます。
前回の記事では、構造化SEOの考え方について解説しました。
今回は、SEO対策を考えている企業のマーケティング担当者に向けて、SEOの考え方について解説します。
企業のマーケティング担当者、個人でブログを執筆しているアフィリエイターの方は、Webサイトを運用する中で必ず出会う「SEO」という考え方について解説します。
SEO(検索エンジン最適化、Search Engine Optimizationの略)について知るには、検索ユーザーの行動、Google社によるアップデート、そしてGoogleの理想の検索エンジンの在り方について考える必要があります。
まずは、Google検索の仕組みについておさらいしましょう。
Google検索とは
Google検索とは、Googleが提供している世界で最も利用されている検索エンジンのことです。
Google検索を使って、インターネット上のさまざまな情報を得たり、ネットショッピングを楽しんだりすることができます。
Google検索を使用する際、検索する人(ユーザー)は検索窓に知りたい単語を入力します。
例えば、京都旅行に行く時におすすめのお土産を知りたい場合は、「京都 お土産」と検索すると、関連するWebページが検索結果に表示される仕組みになっています。

もちろん、「京都 お土産」以外にも「京都 お土産 おすすめ」や「京都府 お土産 人気」のように、同じ情報を得たい場合でも、異なるキーワードを使って検索することがあります。
このように、Google検索を使う検索ユーザーは、得たい情報に応じてあらゆるキーワードを入力し、それに対する解答を得ようとするわけです。
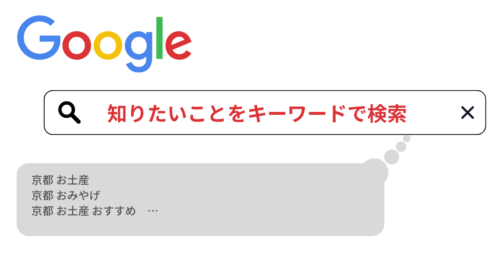
しかしご存知の通り、検索結果として表示されるWebページは1つだけではありません。
関連性の高いとされるWebページが、場合によっては1000件以上も表示されます。
検索ユーザーが、京都ならではのお土産を知りたいと思い、「京都 お土産」と検索したとします。
しかし、全く関係のない検索結果(例えば「犬に食べさせてはいけない食べ物7選!」や「一人暮らしであるとQOLが向上する人気のアイテム5選!」といった記事)が表示されたらどうなるでしょうか?
恐らく、検索ユーザーは「欲しい情報が得られないならGoogle検索を使うのやめよう。」と考えるでしょう。
欲しい情報が書かれた記事が100件目に表示されていた場合も同様です。
ユーザーは「欲しい情報にたどり着くのがここまで面倒なら他の方法で調べよう」と考えてしまうでしょう。
そうすると、Google検索のユーザーは他の検索エンジン、Yahoo!検索やBingなどを利用するようになり、結果としてGoogle社は利益を失うことになります。
つまり、Google社の命題は「いかに検索ユーザーを満足させるか」ということなのです。
Google社の理想の検索エンジン
では、検索ユーザーが満足する検索エンジンとはなんでしょうか?
答えは簡単です。
「知りたいことにズバッと答えをくれる(=適切な検索結果を表示してくれる)」検索エンジンです。
しかし、この実現には2つの課題があります。
【課題1】Google検索はあくまでプラットフォームである
Google社はあくまで、検索できるプラットフォームを提供しているに過ぎません。
世の中にある膨大な情報を、無数の利用者がWebページとしてインターネット上に公開しています。
それらのWebページの中には、正しい情報が記載されていないものや、人の生活を脅かすもの(スパムや詐欺など)もあります。あるいは、既に公開されているWebページの情報をそのままコピーしたコンテンツもあることでしょう。
それらの中から、どのコンテンツがより優れているか、正しい情報かを判断し、最も優れたWebページを検索結果の上位(検索結果の1番目)に表示しなければなりません。
【課題2】ユーザーの検索意図を正確に把握しなければならない
膨大なWebページ、情報の中から優れたコンテンツを見つけることができたとしても、それがユーザーの知りたい情報でなければ意味がありません。
京都の人気のお土産を知りたいユーザーに、「誰でも簡単に作れるふわふわオムライスのレシピ」を紹介しても、ユーザーは満足しないのです。(たとえふわふわのオムライスが作れたとしても、です)
つまり、ユーザーが検索窓に入力したいくつかのキーワードから、このユーザーが何を知りたいのかを適切に読み取る必要があります。
この2つの課題をクリアすることで、Google検索はようやく、検索エンジンとしてあるべき姿になると言えます。
検索意図について:こちら
では、この理想の検索エンジンになるべく、Google社はどのように施策を行ってきたのでしょうか?
Google検索のアップデート
これらの課題の解決策として、Google社はこれまで無数の検索アルゴリズムアップデートを実施してきました。
実は、毎日検索エンジンの至る所で大小さまざまなアップデートが行われています。
日々行われる微細なアップデートを、ただ趣味程度にGoogle検索を使用するだけの方が気付くのは不可能に近いでしょう。
しかし、年に3〜4回程度、大規模なアップデートが行われることがあります。
これを、Webマーケティング業界では「コア アルゴリズム アップデート(もしくはコア アップデート)」と呼んでいます。
この大掛かりなアップデートは、検索結果に大きな影響を与える可能性のあるものを指し、近年では、Google社がこのコアアップデートを実施する際にTwitterで事前に告知するようになりました。
この大小さまざまな規模の検索エンジンのアップデートは、全てユーザーの利便性(ユーザビリティ)を向上するためにGoogle社が行うものです。
その中でも、いくつかの特徴的なコアアップデートには「ペンギン・アップデート」「パンダ・アップデート」などの名称が付けられています。
これまでロールアウトされたコアアップデートをいくつかご紹介します。
パンダ・アップデート
パンダ・アップデート...広告が過剰に掲載されたWebサイトや、低品質なWebサイト(他の記事をコピーして転載しただけのようなWebページ、情報量の少ないWebページなど)が検索結果の上位に表示されないようにし、独自性の高いコンテンツを上位に表示させるためのアップデート。2011年頃から実施されている。ファーマーアップデートとも呼ばれる。サイトの品質の「白黒をはっきりさせる」ことからパンダ・アップデートと名付けられた。
ペンギン・アップデート
ペンギン・アップデート...検索結果の上位に表示をさせるためだけの目的で作られた、意味のないWebサイトや、スパム目的に作られたWebサイトにペナルティを課し、検索順位を大きく落とすためのアップデート。これによって、これまで横行していた悪質な手法でのSEOが無効化され、検索結果のクオリティが向上した。パンダ・アップデート同様、サイトの品質の「白黒をはっきりさせる」ことからペンギン・アップデートと名付けられた。
ハミングバード・アップデート
ハミングバード・アップデート...会話型の検索に対する処理能力を向上するためのアップデート。このアップデート実装前までは、検索する際、「新宿でおすすめの可愛い女子ウケするカフェ」のような会話型のキーワードでは検索意図に沿った結果を表示できないことが多々あった。ハミングバード・アップデートのロールアウト当初はそこまで大きな変化をもたらさなかったが、セマンティック検索(検索の際に入力されたキーワード群から、その意味や検索意図を検索エンジンが正しく認識するための技術のこと)の実現に大きく寄与しており、現在の音声検索や、より正確に検索意図を汲み取ることができるようになった。
Googleのコアアルゴリズムを高速化することからハミングバード(ハチドリ)・アップデートと名付けられた。
ベニス・アップデート
ベニス・アップデート(ヴェニス・アップデート)...検索結果の表示に、検索したユーザーの位置情報を反映するためのアップデート。これによって、下北沢で「カフェ」と検索した場合、自動的に検索ユーザーの位置情報から「下北沢にあるカフェ」を検索結果で表示できるようになった。現在はGoogleマップでも同様にこの仕組みが適用されている。
モバイルフレンドリーアップデート
モバイルフレンドリーアップデート...世の中のスマホ普及率の向上に伴い、これまでのPCでの検索行動に対するアップデートと異なり、スマホの検索結果に対しても最適化されたWebサイトを評価するもの。モバイルフレンドリーではないWebサイトは、画面の幅に対して画像が見切れてしまっていたり、ボタンが小さ過ぎてユーザビリティに欠けるWebサイトを指す。
これらはこれまで行われたコアアップデートのほんの一部ですが、どれも現在の検索行動をより良いものにするための検索アルゴリズムのアップデートであることがわかります。
SEOって結局どう考えれば良いの?
ここでようやく本題です。
Webサイトの管理・運用を考えているあなたが行うべきSEOとはどのようなものでしょうか?
世の中のSEO業者の行うSEO対策は、大きく3通りに分かれます。
- Googleの裏をかこうとするSEO
- Googleのコアアップデート内容に応じて方針を決めるSEO
- Googleの意図を組んで施策を行うSEO
1.は言わずもがな、悪手です。この手のSEOを行ってきた業者は過去に大勢いましたが、ことごとく淘汰されてきました。
一例を挙げるなら、「被リンク数が多いサイトほど上位表示されやすい傾向がある!」とされた時代に、「なら被リンクめっちゃ貼りまくれ!」という施策を行っていた業者は、一時的には順位が上がりましたが、その後のパンダ、ペンギン・アップデートによってペナルティを受け、大きく順位を落とすことになりました。
2.はできれば避けたいSEOのやり方です。なぜなら、Googleは一度のコアアップデートで検索エンジンを最良の状態にするわけではなく、理想(検索ユーザーの満足度を最大化する)に向かって段階的にアップデートしているからです。
これはドル円の為替トレードで分秒単位で動く値動きにいちいち反応してしまうようなものです。
直近の1ヶ月の値動きが、全体として価値が上昇しているのであれば、分秒単位での細かい下落を気にするべきではなく、ただドルを買えば良いのです。
Google検索におけるユーザビリティを最大化するようにアップデートが行われるというのは変わらない事実ですから、Googleが行うコアアップデート1回1回に反応せず、ユーザーが満足するであろうWebサイト作りに専念するべきなのです。
ということで、結論。
3.Googleの意図を組んで施策を行うSEOを推奨します。
もっと正確にいえば、Google検索を利用するユーザーのニーズに最も応えるWebサイト作りをする、これが理想のSEOの考え方だと言えます。
(...コアアップデートを無視しろという意味ではありませんよ)
SEO対策って何をすればいい?
世の中にはさまざまなSEOマーケターがいます。
彼らに「SEOってなんですか?」と問いかけると、さまざまな回答が返ってくるでしょう。
- Google検索でWebページを上位表示させること
- Googleから評価されやすいWebサイトを作ること
- 検索エンジンで上位表示させ、多くの流入を得ること など...
どれも間違いではないですが、個人的には的を射ていない気もします。
ここではSEOを「検索ユーザーの求める答えを適切に、快適に伝えるWebサイト(Webページ)を作ること」と定義することにします。
これを踏まえて、SEO対策は何をすれば良いのでしょうか?
やることは大きく次の5通りです。
- 競合/自サイト分析
- 外部対策
- 内部対策
- コンテンツの拡充
- ユーザー体験の最適化
競合/自サイト分析
まずは、自身のサイトがどのような立ち位置なのかを正確に知る必要があります。
これは言ってみれば学習塾に入塾するためのテストのようなものです。
このテストによって、自分の現在の学力を知ることで、自分のレベルに合った授業を受けられるようになります。
SEOに置き換えると、まずはあなたが運用するWebサイトと、競合としてベンチマークしている他のサイトを診断(入塾テスト)します。
あなたのサイトにはどんなユーザーが、どういったキーワードで流入しているのかをGoogleアナリティクスやGoogle Search Console、そのほかSEOツールを用いて調査します。
そして、次に、それらのクエリ(実際に検索によって使用され、Webサイトに流入したキーワードのこと)があなたのサイトの主旨に沿うものかを確認します。
ユーザーの検索意図(インテント)に対して、正しい解答を提示できているかを知るためです。
もし、クエリがWebサイトのコンテンツに合致しない場合は、Webサイトの流入したユーザーが直帰している可能性が高いです。
その場合は、対策したいキーワードを絞ったコンテンツの作成が必要になります。
クエリを確認し、それがWebサイトのコンテンツと合致していることを確認したら、そのクエリでの現在の検索順位を確認します。
検索順位は、Google Search Consoleで確認できます。
そこで、現在の表示順位が30位以下なら、20位台を始めの目標とし、20位台なら10位以内(検索結果の1ページ目)を目標とします。
また、同じクエリで上位表示されているWebサイトを確認してみましょう。
そのサイトは、あなたのサイトの競合となり、表示順位を競う対象となります。
競合サイトはしっかり分析し、何が自分と異なるのか、どういった点がGoogleから高い評価を受けているのかを知る手がかりとなります。
また、競合サイトにはない、自分のサイトの強みを知ることも大切です。
SEOの第一段階としては、
- 自分のサイトの現状を知る
- 競合サイトの強み/弱みを知る
- 具体的な目標を決める
この3点を意識して進めると良いでしょう。
(既にお気づきの方も多いかと思いますが、SEOはとても長期戦なのです)
外部対策
Googleから高い評価を得る(≒ユーザーにとって最適なWebサイトである)ためには、他サイトからリンクを貼ってもらう(被リンクや外部リンクと言います)ことが重要です。
これを目的とした施策を、ウェブマーケティング業界では外部対策と呼んでいます。
外部のサイトにあなたのWebサイトを参照してもらうということは、あなたの発信するコンテンツが他のWebサイト運用者にとって有益であるとGoogleが判断するための一つの指標になるという意味です。
勘違いしてはいけません。ただ外部リンクを貼って貰えば良いわけではなく、
世間からそのコンテンツの権威性や有用性を認められたWebサイトに参照してもらうということです。
これは基本的にはあなた自身が主体的に動いてどうする、というものではありませんが
より多くのWebサイトからリンクを貼られた方がGoogleから評価されやすい傾向がある、という事実は知っておいて損はありません。
内部対策
外部対策に対して、あなた自身のWebサイトの構成をユーザーが使いやすいように最適化する施策を内部対策と呼んでいます。
内部対策では、GooglebotがあなたのWebサイトの構造を把握しやすいよう、サイトマップを作ったり、ページの階層構造を示すパンくずリストを設置したりします。
コンテンツの拡充
どれだけサイトの構造や側が整っていたとしても、Webサイトそのものが発信している情報が不十分だったり、正確ではなかったりすると、Webサイトを訪問したユーザーの満足度が下がってしまうため、まずはしっかりWebサイトに掲載する情報を増やしていく必要があります。
実際、Googleもランキングを決定する要素として「情報の網羅性」について言及しているため、自身がWebサイトで取り上げたテーマについてはどこまで多くのコンテンツを発信できるかも重要です。
ユーザー体験の最適化
結局、どんなに優れたコンテンツを多く発信していても、それを見たユーザーが使いにくいUI(ユーザーインターフェース)であればリピーターは増えません。
サイトの使い方がよくわからないデザインや、文字フォントが小さすぎて見難い、モバイル端末で見た時に画面内に収まらないなど、UIをユーザーファーストに整えるのはとても大切なことです。使いやすいWebサイトであれば、閲覧ユーザーの滞在時間は長くなり、Googleから評価を受けることにも繋がるため、あくまで利用ユーザーを軸にWebサイトはデザインする必要があります。