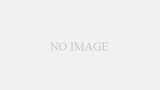この記事は、ウェブアクセシビリティの基本からその歴史的背景、さらにはよくある疑問や実際の利用シーンまでをわかりやすくまとめたものです。ウェブアクセシビリティを初めて学ぶ方でも、ここから理解を深めていただける内容となっています。
ウェブアクセシビリティとは?
ウェブアクセシビリティとは、障がいのある方や高齢者を含むすべての人が、ウェブサイトの情報や機能を平等に利用できるようにするための設計指針です。例えば、視覚障がいを持つ方がスクリーンリーダーでサイトの内容を読み上げてもらうために、画像に代替テキストを付けるなどが挙げられます。
ウェブアクセシビリティはどのように考案されたのか
1990年代にインターネットが一般的に普及する中で、障がいのある方のウェブ利用へのバリアが顕在化しました。これに対し、W3C(World Wide Web Consortium)は1997年にウェブアクセシビリティのための「Web Content Accessibility Guidelines(WCAG)」を発表し、障がい者や高齢者にも使いやすいウェブの指針を示しました。
ウェブアクセシビリティを学ぶ上でつまづくポイント
ウェブアクセシビリティを学ぶ際、多くの人がつまづくポイントは、規格に従ってサイトを構築するための具体的な方法です。たとえば、視覚障がい者向けにスクリーンリーダーが適切に動作するようにするためには、HTMLのタグやARIA属性の使い方など、技術的な知識が必要です。多くの人がこの知識不足でつまづくため、理解の際にはWCAGガイドラインや事例を参考にするのが有効です。
ウェブアクセシビリティの構造
ウェブアクセシビリティは、主に4つの原則から成り立っています:知覚可能、操作可能、理解可能、堅牢です。知覚可能とは、視覚、聴覚、触覚などでコンテンツを認識できること。操作可能は、キーボードや音声など多様な操作方法で利用可能なこと。理解可能は、内容やインターフェイスが分かりやすいこと。そして堅牢は、さまざまな技術やデバイスに対応できることです。
ウェブアクセシビリティを利用する場面
ウェブアクセシビリティは、多くのシーンで役立ちます。例えば、視覚障がい者がオンラインでショッピングする場合や、聴覚障がい者が動画を視聴する際に字幕が必要な場合。また、高齢者が文字サイズを拡大したり、色のコントラストを高めて情報を得る場合など、アクセシビリティは幅広い利用シーンで重要です。
さらに賢くなる豆知識
ARIA(Accessible Rich Internet Applications)は、複雑なウェブコンテンツでもアクセシビリティを確保するために設計されたW3Cの仕様で、各要素の役割を示す属性を付加できます。また、近年の音声アシスタントは、アクセシビリティ向上のために活用されています。
あわせてこれも押さえよう!
- 構造化データ
- ページランク
- レスポンシブデザイン(Responsive Design)
- パンくずリスト
- 行動ターゲティング
ウェブページに関連する情報を整理し、検索エンジンが理解しやすくするためのマークアップです。
Googleが採用するアルゴリズムで、ページの重要度を評価します。
さまざまなデバイスに対応するためにレイアウトを調整するデザイン方式です。
現在のページがサイト内でどの位置にあるかを示すためのナビゲーションです。
ユーザーのウェブ閲覧履歴を分析し、関心に合った広告を表示するマーケティング手法です。
まとめ
ウェブアクセシビリティを理解することで、より多くのユーザーがウェブを利用しやすくなり、企業やサイト運営者にとっても広いユーザー層へリーチすることができます。高齢者や障がいのある方だけでなく、あらゆるユーザーにとって使いやすいウェブ作りは、全体のユーザーエクスペリエンスを向上させるでしょう。