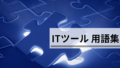本記事では、Slackを初めて知る方にも理解しやすいように、活用例や考案の背景などを交えながら、丁寧にSlackの概要を解説しています。
Slackとは?
Slackとは、チームや組織のコミュニケーションを効率化するためのビジネスチャットツールです。メールよりもスピーディで、チャンネルごとに話題を分けて整理できるため、情報の共有や確認がスムーズになります。Google ドライブやZoomなどの外部サービスとの連携も豊富で、働き方改革を支援するITツールとしても注目されています。
わかりやすい具体的な例
会社のプロジェクト進行でのSlack活用
graph TD A[Slack起動] --> B[プロジェクトチャンネル確認] B --> C[進捗の確認] C --> D[ファイル共有] D --> E[会話へのリアクション] E --> F[作業完了報告] note right of B: 各プロジェクトごとに専用の「チャンネル」を設定 note right of D: Googleドライブと連携して資料共有も可能
Slackではプロジェクトごとにチャンネルを作成することで、関係者のみが情報をやり取りできる環境が整います。ファイルの共有も簡単で、全員が最新の情報にアクセスできる点が便利です。リアクション機能で「見たよ」という意思表示もでき、無駄なやり取りを省けます。
カスタマーサポート部門でのSlackの導入
graph TD A[問い合わせ発生] --> B[チャンネルで共有] B --> C[担当者が反応] C --> D[マネージャーがレビュー] D --> E[回答方針を決定] E --> F[返信内容の送信] note right of A: 顧客からの問い合わせがSlackに転送される note right of C: 対応中の進捗をリアルタイムで共有
サポートチームでは、顧客対応の内容をSlackで共有することで、チーム全体での情報の見える化が可能になります。対応中のメッセージにリアルタイムで反応でき、責任者もすぐに状況を把握できます。結果的に、迅速で正確な顧客対応につながります。
Slackはどのように考案されたのか
Slackはもともとオンラインゲーム「Glitch」の開発過程で誕生しました。プロジェクト管理に必要なチーム内の情報共有に最適なツールがなかったことから、自社用に開発された社内ツールが原型となりました。その後、そのツールが他の企業にも有用であることが判明し、2013年に正式リリースされました。
graph TD A[ゲーム開発Glitch] --> B[チーム内のやり取りに課題] B --> C[独自チャットツールを開発] C --> D[Slackとして製品化] D --> E[世界中の企業に導入] note right of C: 当初は社内ツールとして使用 note right of E: 企業のコラボレーションツールとして進化
考案した人の紹介
Slackを考案したのは、スチュワート・バターフィールド(Stewart Butterfield)氏です。彼は写真共有サービス「Flickr」の共同創業者でもあり、Glitchというゲームの開発中にSlackの原型を生み出しました。ゲームは失敗に終わりましたが、その過程で作られた社内ツールがSlackとして大成功を収めることになります。
考案された背景
2010年代初頭、チームのコラボレーションが複雑化し、メールによるコミュニケーションの限界が問題視されていました。特にスタートアップやリモートワークの普及によって、柔軟かつ高速な連携手段が求められるようになっていた時代背景があります。そのような状況下で、Slackはチャットベースの効率的な情報共有手段として注目されるようになりました。
Slackを学ぶ上でつまづくポイント
多くの人がSlackのチャンネルやスレッドの使い分けに戸惑います。スレッドとは、チャンネル内の特定のメッセージに対する返信をまとめる機能です。これを正しく使わないと、情報が流れて探しにくくなります。また、ZoomやGoogleドライブなどとの連携が多機能すぎて、使い始めは圧倒されることがあります。しかし、これらは慣れれば非常に便利な機能であり、チュートリアルやガイドを活用することで克服可能です。
Slackの構造
Slackは、リアルタイム通信を可能にするWebSocketを使った非同期通信を基本とし、各ユーザーやチャンネルごとにメッセージデータを保存・同期する構造になっています。また、BotやWebhookと連携し、外部アプリケーションとの拡張性を持たせています。チャンネルベースの構造によって、情報が整理されやすくなっているのも特徴です。
graph TD A[ユーザー] --> B[チャンネル構造] B --> C[メッセージDB保存] C --> D[WebSocket通信で同期] B --> E[Botやアプリ連携] note right of D: 非同期通信でリアルタイム更新 note right of E: Webhookによる自動連携も可能
Slackを利用する場面
Slackは、ビジネスや教育機関など、チーム内の情報共有やプロジェクト管理が求められる場面で活用されます。
利用するケース1
中規模企業で複数部署が協力するプロジェクトを進める際、Slackは部門間のやり取りを効率化します。営業・開発・サポートなどの各部署が専用チャンネルを持ち、それぞれの進捗をリアルタイムで共有することで、意思決定のスピードが大幅に向上します。チャットだけでなく、ファイル共有やボットによる自動通知も可能なため、業務全体の生産性向上に寄与します。
graph TD A[営業部] --> B[Slackチャンネル] B --> C[開発部] C --> D[サポート部] D --> E[情報統合] note right of B: 各部門専用のチャンネルを設置 note right of D: 進捗状況や報告を統合管理
利用するケース2
大学や専門学校などの教育機関でも、Slackは学生と教員の情報交換に活用されています。授業ごとにチャンネルを分けることで、課題の共有、質問の受付、参考資料の提供が効率的に行えます。教員は通知機能で学生の進捗を確認し、教育現場でもSlackの柔軟性が発揮されています。
graph TD A[学生] --> B[授業チャンネル] B --> C[教員] C --> D[課題投稿] D --> E[進捗確認] note right of B: 授業単位でチャンネルを構成 note right of E: 通知機能で提出状況を把握
さらに賢くなる豆知識
Slackには「/remind」コマンドという便利な機能があります。これを使えば、チャット上で自分自身やチームメンバーにリマインドを設定できます。また、「Slack Connect」を使えば、社外の企業とも安全にコミュニケーションを取ることが可能です。意外に知られていませんが、Slackには絵文字リアクションを自作できる機能もあり、社内文化の醸成にも一役買っています。
あわせてこれも押さえよう!
Slackの理解を深めるために、関連するITツールも併せて学ぶことで、より実践的なスキルを身につけることができます。
- Microsoft Teams
- Zoom
- Google Workspace
- Notion
- Trello
Slackと似た機能を持つマイクロソフトのビジネスチャットツールで、Office 365との連携に強みがあります。
ビデオ会議に特化したツールで、Slackと連携させることでオンライン会議の招待も簡単に行えます。
Slackと組み合わせることで、ドキュメントやカレンダーなどの管理がシームレスに行えます。
タスクやナレッジの整理に強みがあり、Slackとの連携でチーム内の情報整理がさらに進みます。
カンバン方式のタスク管理ツールで、Slackの通知機能と組み合わせて進捗を把握できます。
まとめ
Slackを理解することで、チームの生産性や情報共有の質が飛躍的に向上します。導入直後は戸惑うこともありますが、日々の業務に馴染ませることで、柔軟で効率的な働き方が可能になります。特にリモートワーク時代においては、Slackの活用が大きな武器となります。