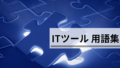本記事では、まだQuipを知らない方に向けて、基本的な特徴から活用方法までを丁寧に解説しています。ビジネスでのドキュメント共有やチーム作業に関心がある方は、ぜひ参考にしてください。
Quipとは?
Quipとは、クラウドベースで動作するドキュメント共有とチームコラボレーションのためのツールです。文書、スプレッドシート、チャット、ToDoリストなどを一元管理でき、共同作業の効率化を図ることができます。
わかりやすい具体的な例
プロジェクトの進行を円滑に管理したいとき
graph TD A[Quipでプロジェクト資料を作成] --> B[メンバーが同時に編集] B --> C[チャット機能でコメントや相談] C --> D[ToDoリストで進行状況を可視化] D --> E[進捗がリアルタイムで共有される] note right of C チャット機能:Slackのような軽い会話が可能 note right of D ToDoリスト:各タスクの担当者と期限が設定可能
プロジェクトで使う資料をQuipで作成し、メンバー全員がリアルタイムに編集します。チャットを使ってその場で相談でき、ToDoリストで誰がどの作業を担当しているのか一目で分かります。
社内マニュアルを全員で作成するとき
graph TD A[新入社員向けマニュアル作成] --> B[各部署が章ごとに執筆] B --> C[Quipで共有し編集] C --> D[社内コメントでフィードバック] D --> E[完成後に全社員へ通知] note right of C 編集履歴が残るため安心 note right of D コメントは特定の行に紐づけ可能
各部署の担当者がマニュアルの章を作成し、Quipに集約することで効率的な編集が可能です。コメント機能を使えば内容の修正や提案もスムーズに行えます。
Quipはどのように考案されたのか
Quipは「分断された業務コミュニケーションの統合」を目的に開発されました。多くの企業が文書とチャット、タスク管理を別のツールで行っていたため、これらを一体化するニーズが高まっていました。
graph TD A[従来の業務フロー] A --> B[文書はWord] A --> C[チャットはSlack] A --> D[タスクはTrello] B --> E[連携が非効率] C --> E D --> E E --> F[Quipが一体化] note right of A 各ツールが独立していて情報が分断
考案した人の紹介
Quipを考案したのは、Facebook元CTOのブレット・テイラー氏です。彼はリアルタイムの共同編集やモバイルファーストのUXに着目し、ビジネスにおける非効率を改善するためのツールとしてQuipを構想しました。2012年にSalesforceと連携を進める形で開発が進み、革新的なコラボレーション環境を提供するに至りました。
考案された背景
2010年代初頭、クラウドコンピューティングとリモートワークの拡大により、複数の業務ツールを同時に使う非効率さが問題視されていました。こうした時代背景の中で、統合型の作業環境を求める声に応じてQuipが誕生しました。
Quipを学ぶ上でつまづくポイント
Quipでは文書作成、チャット、スプレッドシートなどが一つにまとまっているため、初めて触れると「どこから手をつけていいか分からない」と感じる人も多いです。特に、GoogleドキュメントやSlackなどの他のツールに慣れている人は、それらとの操作感の違いに戸惑うことがあります。しかし、各機能がシームレスに連携している点を理解できれば、その利便性をすぐに実感できます。
Quipの構造
Quipは「ドキュメントエンジン」「リアルタイム通信」「コラボレーションUI」の3つの要素で構成されています。ドキュメントエンジンはMarkdownベースで構築され、編集の軽快さを実現しています。リアルタイム通信はFirebaseやWebSocketに近い設計で、遅延のない同期を提供します。UIはSlackやNotionに近い設計思想を取り入れ、直感的な操作が可能です。
graph TD A[Quip構成] A --> B[ドキュメントエンジン] A --> C[リアルタイム同期] A --> D[チャット・タスクUI] B --> E[Markdownで軽量] C --> F[WebSocket類似構造] D --> G[直感的なUX] note right of C 変更は即座に反映される
Quipを利用する場面
Quipはチームでの文書作成やプロジェクト管理の場面で活用されます。
利用するケース1
マーケティングチームがキャンペーン施策の提案書をQuipで作成するケースです。デザイナーが画像案を埋め込み、コピーライターがテキストを編集し、マネージャーがToDoリストで進行を管理します。チャットを使ってリアルタイムに意見を交わせるため、アイデアのブラッシュアップがスムーズに行えます。
graph TD A[施策提案書の作成] --> B[画像埋め込み] B --> C[文章校正] C --> D[ToDoで進捗管理] D --> E[チャットで意見交換] note right of D 作業進捗が一目で把握可能
利用するケース2
人事部門が社内アンケートをQuipで実施するケースです。アンケート項目を文書内に記載し、リンク共有で全社員に展開します。集計結果をスプレッドシートで可視化し、改善施策の提案までを1つのQuipファイルで完結できます。
graph TD A[社内アンケート作成] --> B[社員に共有] B --> C[回答を集計] C --> D[改善案を提案] note right of C スプレッドシートで集計が視覚化される
さらに賢くなる豆知識
Quipはモバイルアプリが非常に高機能で、PC版と同等の操作が可能です。外出先からでも共同編集ができ、通知機能で即座に更新を把握できます。また、QuipはSalesforceと連携しており、CRMデータとドキュメントをシームレスに統合できる点も大きな強みです。
あわせてこれも押さえよう!
Quipの理解において、あわせて学ぶ必要があるツールについて5個のキーワードを挙げて、それぞれを簡単に説明します。
- Notion
- Slack
- Googleドキュメント
- Confluence
- Dropbox Paper
ドキュメントとデータベースが統合されたオールインワンツールで、自由度の高い管理が可能です。
ビジネスチャットツールで、チーム間の素早い情報共有に適しています。
クラウドベースの文書作成ツールで、リアルタイム共同編集が強みです。
ナレッジマネジメントに強みを持つWikiベースのツールです。
シンプルな構造で、直感的に共同作業が行えるクラウド文書ツールです。
まとめ
Quipを活用することで、ドキュメント作成からタスク管理、チャットまでを1つのツールで完結できます。これにより、チーム間の連携や作業効率が大幅に向上します。日常業務の見える化や属人化の解消にもつながり、組織全体の生産性向上に貢献します。